今日もブログにお越しくださりありがとうございます!
No.3 Runner’s worries: 記録の伸び悩み
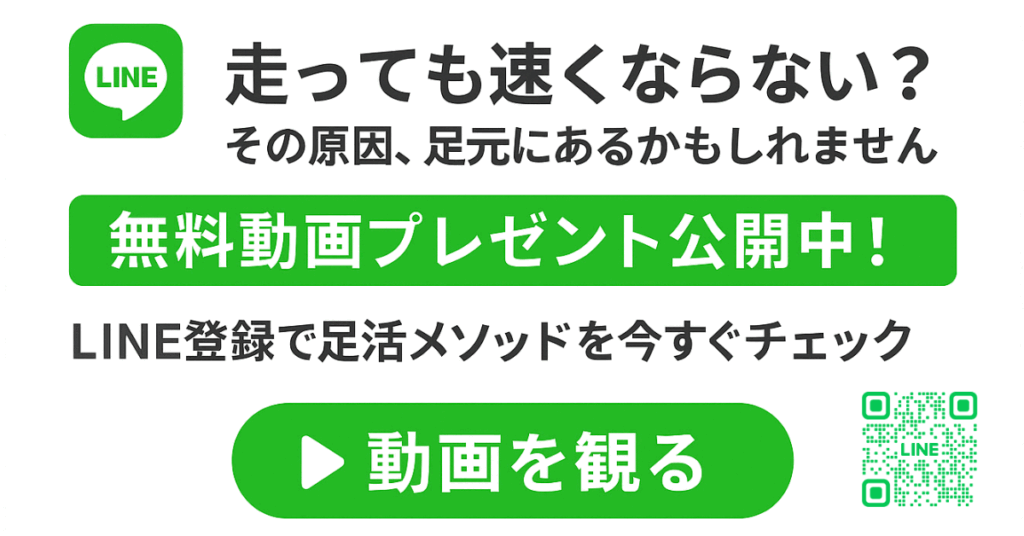
序章:40代ランナーに訪れる“成長の停滞”
「去年よりも走り込んでいるのに、なぜか記録が伸びない」
「サブ4は達成したけど、その先が見えない」
「疲労ばかりが蓄積し、ケガも増えてきた」
40代マラソンランナーの多くが、ある時期に突如として感じ始める“成長の停滞感”。それはまるで、これまで登ってきた階段が突然なくなってしまったかのような、そんな喪失にも似た感覚かもしれません。
実はこの現象は、あなただけに起きていることではありません。多くの市民ランナーが40代を境に「距離を増やしても成果が出ない」「タイムが頭打ちになる」といった悩みに直面しています。
ここで勘違いしてほしくないのは、「年齢のせい」とだけで片付けることの危険性です。確かに40代を過ぎると身体的な衰えが始まるとされます。しかし、それは“ピークを過ぎた人”の話。まだ成長の途中である市民ランナーにとって、加齢は必ずしもネガティブ要因ではありません。
むしろ問題なのは、「仕事・家庭・時間・環境」といった生活全体の“コストの限界”と、そこから生まれるトレーニング上の“見えない天井”です。
第1章:なぜ40代になると伸び悩むのか?──3つの根本原因
「何をやっても、以前のような成長を感じない」
──40代のマラソンランナーが抱えるこの伸び悩みは、単なる“気のせい”でも“老化”のせい”でもありません。そこには明確な原因が3つ存在します。
原因①:現在の練習では、もう“足りない”
20代、30代の頃には、ただ距離を積む、週に一度スピード練習を入れる、月に一度ロング走をする――といった「基礎的な練習」で記録は順調に伸びていったかもしれません。
しかし40代になると、ランニング経験も10年近くになってくる人が多く、これまで積み重ねた練習の“蓄積”がすでに飽和状態に達し始めます。いわゆる「収穫逓減の法則(やればやるほど伸び幅が小さくなる)」が働くのです。 (しゅうかくていげんのほうそく)
つまり、過去と同じメニューでは、次のステージに必要な刺激として“不足”してしまう。にもかかわらず、同じやり方にこだわり続けてしまうのです。
原因②:練習量を増やしたくても、もう増やせない
さらに厄介なのが、社会人としてのライフスタイルです。40代ともなれば、仕事は責任ある立場になり、家庭では子育てや介護なども重なってくる時期。単純に練習時間を「増やす」ことができない状況にある方が大多数です。
「これ以上走る時間は取れない」
「週末のロング走ですら、家族に気を使ってしまう」
このような生活的制約が、トレーニングの可能性にブレーキをかけているのです。
原因③:環境や生活スタイルは変えられない
「じゃあ、もっと走れるように生活を変えればいいのでは?」という声もあるかもしれません。しかし、40代はもう“生活を大きく変えること”が難しい年代です。
家族との関係、仕事上の立場、住む場所、日々のルーティン──どれもが積み重ねてきた人生の中で形成された「変えがたい現実」なのです。
つまり40代ランナーは、「成長するには現状が足りない」と分かっていながらも、「それ以上やる時間も余力もない」「生活は変えられない」という“ジレンマ”の中にいるのです。
ここに、加齢による疲労回復の遅れや怪我のリスクが加われば、ますます悪循環に陥ります。
しかし、これは「絶望的な袋小路」ではありません。
むしろ、ここを突破することができれば、あなたは新たなレベルの走力と身体感覚を手に入れることができるのです。
では、その突破口とは何か?
次章では、誤解されがちな“加齢による衰え”の真実と、本当の原因である“限界環境”について深掘りしていきます。
第2章:加齢ではなく“限界環境”こそが壁である
「もう40代だから」「年齢的に無理なのかな」
──そう感じて、心の中で“諦めの種”が芽生え始めたランナーは少なくないでしょう。確かに、加齢による変化は無視できない要素です。しかし、池上英之氏も指摘しているように、多くの市民ランナーにとって「加齢」は本質的な伸び悩みの原因ではありません。
むしろ本当に大きな影響を与えているのは、“生活と環境の限界”です。
「限界環境」とは何か?
限界環境とは、走力の向上を阻む生活的・社会的な制約の総称です。
- トレーニング時間がこれ以上取れない
- 家族との時間を削れない
- 仕事のストレスが多く、疲労が抜けにくい
- 睡眠時間が不規則でリカバリーが追いつかない
- 食事も外食が多く、栄養管理ができていない
──どれも「あなたが悪い」のではなく、“生活そのもの”が限界に達しているのです。
このような環境の中で、「距離を増やす」「インターバルを詰め込む」「ロング走を週2回やる」などの方法は、むしろオーバートレーニングと故障を引き起こす原因になってしまいます。
実は“加齢”にもチャンスがある
持久力というのは、短期間で劇的に伸びる性質のものではありません。筋力やスピードは若いうちにピークを迎えますが、持久力は“年単位”で少しずつ積み重ねていく性質があります。
つまり、ランニング歴10年未満の40代であれば、まだピークに達していない可能性が高く、むしろ「ここから本格的に伸びる」チャンスが残されているのです。
「自分のピークに到達するには15年はかかる」といわれるランナーもいます。
この視点に立てば、40代は“衰えの入り口”ではなく、“完成への助走”とも言えるでしょう。
問題は“戦い方”が変わったことに気づいていないこと
これまでと同じやり方では、これまで以上の結果は出ません。若い頃と同じメニュー、同じ量、同じスタイルで練習しても、壁は越えられません。
ここに気づかない限り、40代以降のランナーは「故障→回復→焦って練習→再び故障」のスパイラルに陥ってしまいます。
だからこそ、ここで必要なのは「新しい戦い方」なのです。
次章では、その“戦い方の第一歩”として注目されている「リカバリー戦略」について詳しく解説していきます。
第3章:打破のカギは“リカバリー”にあり
これまで多くの市民ランナーが見落としてきた、けれど本当は最も重要な要素──それが「リカバリー(回復)」です。
ランニングにおいて“練習”は確かに大切ですが、練習によって得られる成果は「リカバリーの質」に大きく左右されます。むしろ、練習後にしっかりと回復できなければ、パフォーマンスはむしろ低下してしまうのです。
リカバリーは“練習しないこと”ではない
リカバリーと聞くと、「休むこと」と解釈されがちですが、それは誤解です。
真のリカバリーとは、「トレーニングによってダメージを受けた身体を、最大限の回復力で修復・強化するプロセス」を意味します。
そしてそのためには、以下の2つの柱が欠かせません。
① 栄養
疲労回復に必要なエネルギーと、筋肉修復に必要なタンパク質・ビタミン・ミネラルを、日々の食事でしっかり補うこと。特に40代以降は胃腸の吸収力も変わってくるため、「何を食べるか」と同時に「いつ食べるか」「どれだけ吸収されるか」まで意識する必要があります。
- 炭水化物は練習前後にしっかり摂る
- タンパク質は1日3回以上に分けて補給
- 鉄分や亜鉛、マグネシウムなどミネラルも意識する
② 睡眠
「眠っている間に身体は強くなる」と言われるように、睡眠は超回復の鍵です。
とくに成長ホルモンの分泌が最大化されるのは、入眠から90分以内の深い睡眠時。この時間帯を質の高い睡眠にすることができるかどうかが、翌日の回復状態に直結します。
- 就寝90分前にはスマホやPCを見ない
- 寝る前に湯船で体温を上げておく
- カフェインは午後3時以降は避ける
こうした生活習慣の積み重ねが、回復力を引き上げ、同じトレーニング量でも“吸収率”を高めるのです。
なぜリカバリーが伸び悩みに効くのか?
40代で伸び悩む理由の多くは、「練習量の限界」にぶつかっていることにあります。
つまり、「これ以上の量は増やせない」のであれば、今ある練習を、どれだけ効率よく成果に変えられるかが最も重要になってくるのです。
このとき、リカバリーは「練習の質を引き出す最大の武器」となります。
- 昨日より軽く、スムーズに走れた
- トレーニング後の疲れがすぐ取れた
- 体調の波が小さくなった
こうした変化は、地味ですが確実に「次の一歩」を引き出してくれる兆候です。
見落とされがちな“日常”にこそ、成長のタネがある
ランナーにとって、練習だけが成長の場ではありません。むしろ、練習と練習の“間”にある日常生活こそが、走力の基盤を決めているのです。
リカバリーは練習と同じくらい“戦略的”に設計すべき要素なのです。
次章では、リカバリーと並んで重要な「練習の目的と組み合わせの見直し」について解説します。
第4章:練習の「目的」と「組み合わせ」を見直せ
リカバリーの質を高めた次に見直すべきなのが、練習の「内容」そのものです。
多くのランナーが“伸び悩み”に陥るのは、練習の目的が曖昧なまま、過去の成功体験やルーティンに頼っているからです。
ここで重要になるのが「練習の目的を明確にすること」と「練習の組み合わせを再設計すること」の2点です。
① 練習の「目的」を明確にする
あなたが今やっているその練習の目的は何ですか?
- 持久力を鍛えたいのか
- レースペースを体に刻みたいのか
- 筋持久力を高めたいのか
- 回復走としての意味があるのか
例えば、「40km走」とひとことで言っても、以下のように目的は大きく異なります。
- レースペースで追い込む → 実戦に近い刺激を与える
- ゆっくり長く走る → 脚づくり・エネルギー消費効率の向上
- ペースビルドアップで走る → 後半粘る力の強化
これらの目的を明確にせず、ただ「いつものルーティンだから」「長く走っておけば安心」という理由で実施していると、効率は激減してしまいます。
意図のない練習は、伸び悩みを助長するだけです。
② 練習の「組み合わせ」を変えてみる
練習の負荷を高めるには「時間を増やす」だけではなく、練習同士の組み合わせを工夫するという方法があります。
たとえば──
- 土曜:閾値走 → 日曜:ロングジョグ
→ 有酸素+無酸素系の組み合わせで疲労耐性を高める - 水曜:インターバル → 金曜:テンポ走 → 日曜:30km走
→ スピード〜持久力への移行期トレーニング
このように刺激の種類を意図的に重ねることで、時間を増やさずともトレーニング効果を最大化できます。
「練習の目的と組み合わせの両方を変えることで、さらなるレベルアップが図れる」と考えます。
“変化をつけること”が成長を引き出す
40代は時間も体力も限られているからこそ、「少ない練習で最大の効果を得る戦略」が重要です。
そのためには、ただがむしゃらに練習を詰め込むのではなく、
- 今の練習は何を目的としているのか?
- 他のメニューとどう連携しているのか?
- 今の課題に対して最適な組み合わせか?
こうした問いを自分に投げかける習慣が、あなたの練習に“意味と構造”を与えます。
そして、その変化こそが、停滞を突破するエネルギーになるのです。
次章では、練習内容の見直しだけでは届かない、“無意識の思い込み”──心理的盲点(スコトーマ)について解説します。
この盲点を外すことが、40代以降のランナーにとって最も深いブレイクスルーにつながるかもしれません。
第5章:心理的盲点(スコトーマ)を外す力
「やることはやっているのに、なぜか結果が出ない」
「これ以上何を変えればいいのか分からない」
──そんな壁にぶつかったとき、最も見直すべきなのは、“自分では気づけない思い込み”です。
これを「心理的盲点(スコトーマ)」と呼び、伸び悩みを打破するための最大のポイントとなります。
なぜ、盲点に気づけないのか?
人間は、日常生活のほとんどを“自動化された判断”で生きています。
たとえば、ホテルに入れば自然にフロントへ行き、「チェックインをお願いします」と言える。これは過去の経験や学習に基づいた「ブリーフシステム(思い込みによる判断の省略装置)」が働いているからです。
このブリーフシステムは、効率的に生きるうえではとても便利ですが、ランナーにとっては時に成長の妨げにもなります。
「週末は30km走をしないと不安」
「LSDはやらないと落ち着かない」
「レース前はスピード練習を減らすのが常識」
──それ、本当に“正解”でしょうか?
もしかすると、それらの「常識」は、あなたが成長できた“過去の段階”では有効だったもの。でも今のあなたには、その思い込みが壁になっているのかもしれません。

スコトーマを外すにはどうすればいい?
この盲点を外すには、いくつかの方法がありますが、もっとも効果的なのは、
“自分より知識や経験のある人に教えを請うこと”
です。
自分では気づけない部分だからこそ、他者の視点が必要なのです。たとえば:
- 実績あるトレーナーやコーチ
- 独自の方法論を持つランナー
- 自分が経験していないトレーニング環境に身を置いている人
こうした人との対話や観察は、思考の枠を超えるきっかけになります。
実力実績のあるアスリートも「私も今でも他人に教えてもらっている」と正直に語っています。自身のファッションをコーディネートするために、全国大会入賞経験のある友人に依頼したエピソードは、専門外の領域では「人に頼ることこそが最善」であると教えてくれます。
無意識の“枠”を外すと、走りが変わる
ランニングに限らず、成長を加速させる人たちは、いつも「常識を更新し続けている人たち」です。40代は、まさにその“アップデートのタイミング”。
- 本当に今のフォームは効率的か?
- レース戦略は自分に合っているのか?
- ケアや補強トレーニングは必要十分か?
そんな問いを持ち、「今の自分」をフラットに見つめなおすことが、次の扉を開く鍵となります。
第6章:40代以降に持久力が伸びる本当の理由
「40代からでも、まだ伸びるんだろうか?」
多くのランナーがこの疑問を抱えています。
確かに、加齢とともに筋力や瞬発力、回復力が少しずつ落ちていくことは事実です。しかし──
「持久力」だけは例外なのです。
持久力というのは長い年月をかけて積み上がる資産のようなもの。短期間で劇的に伸ばすことは難しいですが、10年、15年という時間をかければ、40代・50代でも着実に進化し続けます。
ランニング歴が10年未満なら、まだ“成長期”
ここで大切なのは、「年齢」ではなく「ランニング歴」で考えること。
例えば、40歳でランニングを始めた人が50歳になったとします。ランニング歴はまだ10年。持久力が本格的に発展するには15年程度の継続が必要とも言われているため、まだピークの手前にいるわけです。
つまり──
年齢で区切るのではなく、積み重ねの年数で判断せよ
ということです。
年齢を言い訳にしない市民ランナーたち
事実、市民ランナーの中には40代後半や50代で自己ベストを更新し続けている人が少なくありません。
- 初マラソンが45歳。4年後にサブ3達成
- 50代でフルマラソン2時間50分台
- 60代でウルトラマラソン完走を継続
彼らの多くは、持久系スポーツにおける“熟成の価値を理解し、地道にコツコツと取り組んでいます。
走力とは、トレーニングだけではなく、「生活習慣」「メンタル」「経験」「知識」など、複数の要素が積み重なって形成される“複合的な能力”です。
そして、こうした“見えない力”は、むしろ年齢を重ねた人の方が高まっているケースも多いのです。
成長が“ゆっくり”だからこそ、面白い
40代以降のランナーは、20代のような「劇的な変化」は起きづらいかもしれません。
でも、それは「ゆっくりと、確実に成長している証拠」でもあります。
- 以前は20kmでバテていたのに、今は30kmも楽に走れる
- 心拍数の安定感が増してきた
- ペース感覚が自然と身についた
こうした“小さな進化”を積み重ねることで、数年後には驚くほどの成長を遂げることができるのです。
「年齢=下り坂」という時代は終わった
科学的にも、持久系スポーツにおいてはピーク年齢が40代後半〜50代前半にあるという研究結果も存在します。とくにウルトラマラソンやアイアンマンなど、持久力と戦略が物を言う競技では、その傾向が顕著です。
つまり、「もう年だから」と思ってブレーキをかけるのは、自分の可能性を狭めているだけなのです。
では、実際に40代で“壁を破った市民ランナーたちは、どのようにその扉を開いたのでしょうか?
第7章:成功者に学ぶ──「脱・伸び悩み」ランナーの具体例
理屈や理論だけでは、心は動きません。
「自分にもできるかもしれない」と思えるのは、誰かの実例に触れたときではないでしょうか。
ここでは、実際に“伸び悩み”の壁を乗り越えた40代・50代の市民ランナーたちの具体的なケースを紹介しながら、そこに共通するエッセンスを探っていきます。
ケース①:大田原マラソンで2時間36分優勝した市民ランナー(女性・40代)
この女性ランナーは、出産や育児を経てランニングを再開したものの、40代になってから思うようにタイムが伸びず、故障も増え始めていました。
そこで彼女が取り組んだのは、
- 生活リズムの見直し(特に睡眠と食事)
- 週2回の質の高いスピード練習に絞る
- メンタルトレーニングを取り入れ、自分の限界を“思い込み”から解放
結果、3年かけて少しずつ自己ベストを更新し、ついに大田原マラソンで市民ランナー優勝という快挙を達成。彼女は「変わったのは走りよりも、考え方だった」と語っています。
ケース②:サブ3.5からのリスタート(男性・47歳)
会社員としてフルタイム勤務しながら走り続けてきた彼は、サブ3.5を達成して以降、3年間記録が伸びませんでした。
仕事のストレスや家族との時間の確保もあり、思い切った練習量は確保できず、常に「もう限界かな」という気持ちがあったそうです。
そんな彼が取り組んだのは、
- 練習日誌の細分化と振り返り習慣
- 週ごとの“テーマ練習”の導入(スピード強化週・フォーム意識週など)
- 月1回だけ“本気で自分を試す日”を設ける
この“試す日”は、フォーム撮影やトレイル走など、遊び心もある内容で、「数字」以外の成長実感を得る工夫でした。
半年後には、心肺機能や脚力のバランスが整い、PB(パーソナルベスト)を10分更新。本人曰く、「記録よりも、また走るのが楽しくなったことが一番の収穫」。
ケース③:家庭最優先でも成長できた(女性・50歳)
この方は、子育て・パート勤務・家事をこなしながらもランニングを続けていました。
練習時間は1日30分が限界。それでも「成長したい」という気持ちを諦めきれず、下記のような戦略をとりました。
- 平日は短時間で質を求める「効率トレ」
- 食事でリカバリーを徹底管理(疲労感が激減)
- 月1回、専門家の指導を受けて“正しい努力”を学ぶ
彼女は「走る時間が少ないからこそ、“何をするか”を真剣に考えるようになった」と語ります。結果として、走るたびに「今日はいい感じだった」という実感が持てるようになり、2年間でタイムも大きく改善。
共通点は“考え方の変化”
これらのランナーに共通しているのは、「時間があったから」「身体能力が優れていたから」ではありません。
自分の限界に気づき、それでも成長をあきらめなかったこと、
そして「やり方」ではなく「考え方」を変えたことです。
あなたも、日々の中で「変えられること」がきっとあるはずです。
第8章:伸び悩みは「限界」ではなく「深化」の兆し
ある時から、タイムが伸びない。疲労が抜けにくくなる。やる気も少しずつ薄れていく。
そんな経験をしているなら、あなたは“走りの本質”に近づきつつあるのかもしれません。
「もうこれ以上は伸びないかもしれない」
──そう思ったときこそ、次のステージへの入口です。
それは、“がむしゃらに走っていたフェーズ”から、“自分を深く知るフェーズ”への転換点。
つまり、伸び悩みは停滞ではなく、「深化のサイン」なのです。
走力の天井を超えるには、「考える走り」へ
初心者の頃は、距離や本数を増やすことでタイムは着実に伸びていきます。
しかし、ある程度のレベルに達すると、単純なボリューム増加では打破できない“壁”が現れます。
このとき必要なのは、次のような視点です:
- なぜこの練習をやるのか?
- 自分にとって、今一番必要な負荷は何か?
- 日常生活や身体のクセが、走りにどう影響しているか?
こうした問いかけが、単なる練習を「自分に最適化されたトレーニング」へと昇華させます。
つまり、壁を超えるためには「考える力」が必要なのです。
探究する人が、次の扉を開く
ランニングを長く続けるうえで、最も大切なのは「自分なりの楽しさ」を見つけることです。
- フォームの改善にハマる人
- 栄養学を学び始める人
- トレーニング理論を掘り下げる人
- メンタルや集中力の研究をする人
- ランニングギアを試しまくる人
こうして「ただ走る」ことから、「走りを探究する楽しみ」へと意識が変わったとき、あなたは新しいフェーズに足を踏み入れます。
この過程は、他人から見れば些細なこだわりに映るかもしれません。
でも、自分にとっては「一歩の深み」がモチベーションになるのです。
好奇心が“停滞”を超えていく
あるときは、「フォームのクセを1つ直しただけで10秒縮まった」
あるときは、「睡眠を見直したら、朝の走りが軽くなった」
あるときは、「トレーニングの順番を変えたら、疲労感が激減した」
こうした“小さな変化”の積み重ねこそが、本当の意味での成長です。
- 年齢を重ねても記録が更新できる
- 以前より故障が減る
- 毎回の練習に意味と手応えを感じる
それは、好奇心と試行錯誤がもたらす副産物なのです。
“自分だけの走り”が、最強のモチベーションになる
他人のタイムや方法ではなく、自分のペース、自分の目標、自分の楽しみ方。
そこに意識が向いたとき、ランニングは単なる競技や習慣ではなく、自己探求の旅になります。
数字だけに縛られない豊かさ。
昨日よりも「走ることが面白い」と思える毎日。
そうした“深化の走り”は、むしろ40代以降にこそふさわしいスタイルかもしれません。
第9章(まとめ):40代から本当の成長が始まる
走ることに真剣になればなるほど、壁にぶつかります。
そして、壁の先に進もうとしたとき、人は初めて「走るとは何か?」「自分にとっての成長とは何か?」と、深く考えるようになります。
この深掘りこそが、40代からのマラソンにおける本当の成長の始まりです。
伸び悩みは「限界」ではなく「入口」
走力が伸びない。疲労が抜けない。ケガが増えた。
──こうした現象に直面したとき、多くの人は「自分にはもう無理なのかもしれない」と感じます。
でも実際には、それは限界ではなく「変化の必要性」を知らせるサインです。
- 練習を見直すタイミング
- リカバリーや栄養に目を向けるべきサイン
- 心の持ち方を調整するチャンス
つまり、走りの質を“深化”させる入口なのです。
今こそ、やるべき3つのこと
この章までに紹介してきた、40代以降のランナーがやるべきことを整理すると、次の3つに集約されます:
1. リカバリーの質を上げる
栄養・睡眠・ストレス管理を整えることで、限られた練習の“吸収率”を最大化する。
2. 練習の目的と組み合わせを最適化する
「何のためにこの練習をするのか」を明確にし、パズルのように練習メニューを組み合わせていくことで、少ない練習でも大きな成果を得られる。
3. 固定観念を外す
「こうあるべき」「これが常識」と思い込んでいることを一度リセットし、自分に合った方法を模索する柔軟さを持つ。
この3つを日々意識するだけで、あなたの走りは着実に変わっていきます。
自分だけの「ランニング哲学」を持とう
40代からのランニングは、若い頃のような派手なタイム更新だけが目的ではありません。
- 仕事や家庭と両立しながら、どう走り続けるか
- 年齢に応じた変化を受け入れ、どう工夫するか
- 限られた資源(時間・体力)で最大の成果を出すには何が必要か
こうしたテーマに向き合いながら、自分だけの「走りの哲学」を確立していく旅。
これは、他人と競うものではなく、自分の“納得”と“継続”を追求するプロセスです。
最後に──まだ、伸びます
何歳からでも、走りは変えられます。
むしろ、今までと違った角度で自分を見つめ、学び、工夫し、進化できるのが40代以降です。
「これまでのやり方」で頭打ちになったら、
「これからの走り方」を始めてみましょう。
きっと、あなたの中に眠っていた「まだ伸びる力」が目を覚ますはずです。
📌 あなたのランニング人生は、まだまだ続いていきます。
この一歩が、次のステージの始まりです。
公式LINEにご登録お願いします。
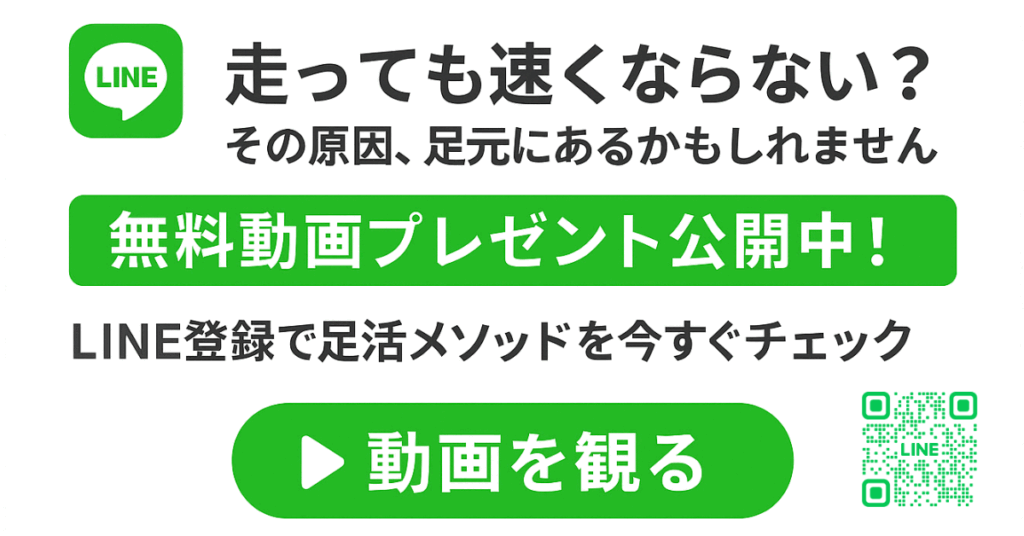
お知らせ:足活体操教室(足から全身を整えて楽しく運動できる体をつくる)
内容: ブログ内参考
足からの整体ケア&全身体操
場所:北九州小倉北区中井4-5-24-1F:のうだ整骨院内(Tel:093-563-3325)
時間:午前11時~12時
料金:入会金:5,000円 月会費:4,000円
個別指導:1時間:10,000円(予約制:オンライン可)



