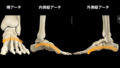No.4 Runner’s worries: 怪我の予防と対処
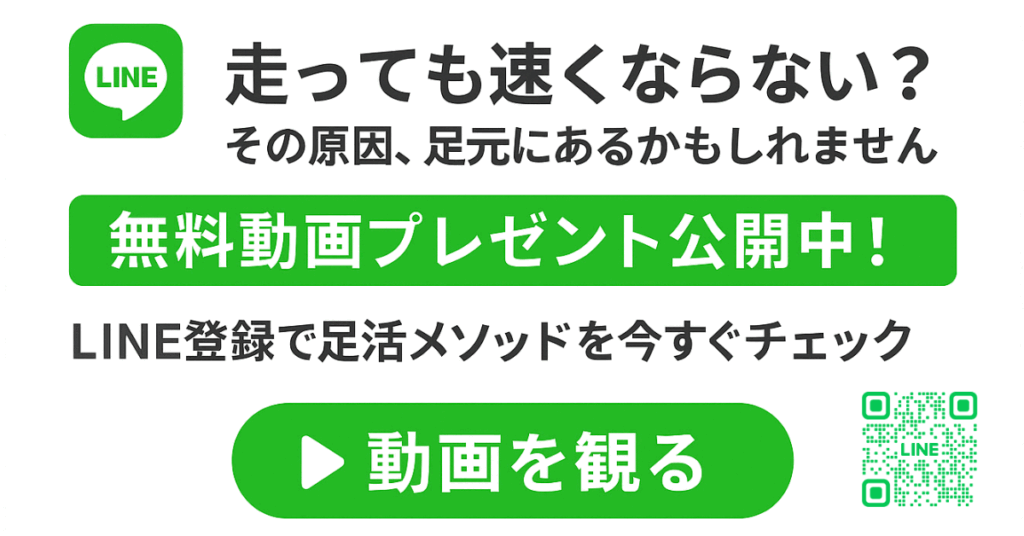
ランナーの相談内容:足底腱膜炎
私は30代後半のマラソンランナーです。ランニングが生活の一部となり、ほぼ毎日のようにトレーニングを続けてきました。しかし、最近、朝起きた時や走り始めに足の裏に強い痛みを感じるようになりました。
最初は「ちょっと疲れているのかな?」と軽く考えていましたが、日に日に痛みが増していきました。特に起床直後や練習開始の数分間は足裏が固まったような感じで、痛みのためにスムーズに走り出せません。しばらく走り続けると痛みはやや軽くなりますが、練習後や休息後は再び痛みが戻ってきます。
心配になり調べてみると、症状は「足底筋膜炎」という怪我にとてもよく似ていました。色々調べた結果、足底筋膜炎の場合は足底のマッサージやストレッチを行ったり、アーチサポート付きの靴を履いたりすると改善が見込めるということでした。
しかし実際、どのくらいの頻度でどのようなマッサージやストレッチを行えば良いのか、またアーチサポートの靴を選ぶ際に気をつけるポイントなど、まだ具体的な方法がよく分かりません。痛みと上手く付き合いながら、ランニングを続けるためにはどうしたらいいのでしょうか?何か具体的なアドバイスがあればぜひ教えていただきたいです。
序章:よくある症状と足底筋膜炎が長引く理由
朝起きて一歩目を踏み出した瞬間、足裏やかかとに刺すような痛み──ランナーであれば一度は耳にしたことがある「足底筋膜炎」の典型的な症状です。休息後(睡眠や長時間座った後)に足を地面につけるとき特に痛みが強く、数分歩くと和らぐという特徴があり、走り始めにも足裏に不快感を覚え、ウォームアップが進むと痛みが減ることがあります。しかし、運動後や長時間の立ち仕事の後に再び痛みがぶり返すのも足底筋膜炎の厄介な点です。
なぜ足底筋膜炎の痛みは長引きやすいのでしょうか?
足底筋膜炎は足裏の筋膜に生じた微細な損傷(マイクロテア)と炎症に端を発する障害ですが、慢性化すると筋膜の変性へ進行し、治りづらくなります。足の裏は日常的に負荷がかかる部位であり、完全な安静が取りにくいことが回復を遅らせる一因です。痛みを抱えながら走り続けたり日常生活で足を酷使したりすると、損傷と修復のサイクルが絶えず繰り返され、なかなか完治に至らないため治癒に時間がかかり、無理をすれば炎症が慢性化してしまうのです
さらに、足底筋膜炎はランナーに非常に一般的な障害です。ある報告では、ランニングが関連する全足部傷害の約10%を足底筋膜炎が占め、ランナー全体の最大22%が生涯に一度は経験するともいわれています。特に走行距離を急激に増やしたときや、硬い路面での練習により長引きやすい傾向があります。実際、足底筋膜炎は早期対応しないと悪化して長引いてしまいます。だからこそ、本記事では足底筋膜炎の原因から最新の治療・予防策まで科学的根拠に基づいて解説し、ランナーが賢くこの痛みと向き合う方法を探っていきます。
第1章:足底筋膜炎の根本原因を知る
足底筋膜炎を克服・予防する第一歩は、なぜ自分の足に痛みが生じたのか根本原因を理解することです。市民ランナー(特に中級〜上級者)の場合、以下のような要因が複雑に絡み合って足底筋膜への負担を増大させていることが少なくありません。
筋肉の硬さ(ヒラメ筋・腓腹筋)による影響
ふくらはぎの筋肉(腓腹筋とヒラメ筋)の硬さは足底筋膜炎の大きな要因です。足関節の背屈(つま先を上に向ける動き)の可動域が制限され、歩行やランニング時にかかとが十分持ち上がらず足底筋膜に過剰な張力がかかります。臨床の背屈制限は足底筋膜炎の発症リスクとして指摘されています。
特にヒラメ筋は膝を曲げた姿勢で足関節を支える筋肉で、ランニング後半の疲労時や坂道走で酷使されます。ヒラメ筋が硬直すると着地時の衝撃を十分吸収できず、足底筋膜が引き伸ばされてしまいます。一方、ふくらはぎの表層にある腓腹筋は膝を伸ばした状態で働き、スピード練習や坂道ダッシュ時に負荷がかかります。腓腹筋が短縮するのがわかります。
実際、ふくらはぎのストレッチ不足や筋肉の柔軟性欠如は足底筋膜炎の主要因であり、筋肉が硬いと足底筋膜を強く引っ張って痛みを引き起こします最近カーフストレッチを怠っていたり、デスクワーク続きで足首が固まっていたりする場合、この筋肉ているかもしれません。
カーフストレッチ:
壁に向かって立ち、手を壁につきます。ストレッチする側の足を一歩後ろに引き、かかとを地面につけたまま膝を伸ばして、前の膝をゆっくり曲げていきます。ふくらはぎが伸びる感覚を感じたところで15~30秒キープしましょう。左右交互に2~4セット行います。膝を曲げる角度を変えることで、腓腹筋(膝を伸ばした状態)とヒラメ筋(膝を軽く曲げた状態)の両方を効果的にストレッチできます。
足関節の過回内(オーバープロネーション)とアーチの問題
走行時の足の動き(バイオメカニクス)にも目を向けましょう。足を着地した際に必要以上に内側へ倒れ込んでいないでしょうか?これが足関節の過回内(オーバープロネーションョンでは足の縦アーチが潰れるように低下し、足底筋膜が通常以上に引き伸ばされてしまいます。その結果、筋膜の付着部である踵小断裂や炎症が起こりやすくなります。
扁平足(土踏まずが低い足)のランナーはプロネーションが大きく足底筋膜炎になりやすいことが知られています。実際、扁平足で足が内側に過剰回内する人では、足底筋膜に強い牽引ストレスがかかり、炎症を起こしやすいのです。一方、ハイアーチ(土踏まずが高い足)の人もクッション性が低く、プロネーションが不足(過回外)しがちで、衝撃を十分吸収できません。つまり足裏のアーチが低すぎても高すぎても足底筋膜炎のリスクとなりますが、一般的にはオーバープロネーション(過剰回内)の方が頻度も高く典型的な原因です。
ご自身のランニングシューズの靴底の減り方を観察してみてください。内側の減りが極端に強い場合、走行時に過度なプロネーションが起きている可能性があります。また、鏡の前でリラックスして立ったとき、足首が内側に崩れて土踏まずが潰れて見えるなら、走っている最中も足底筋膜に負担が集中している恐れがあります。
ランニングフォームやシューズ選びの問題

トレーニング内容やフォーム、シューズといった外的要因も見逃せません。急激な練習量や強度の増加:これが最もよくある原因です。フルマラソン前に週の走行距離を急激に増やしたり、インターバル走や坂道ダッシュを急に始めたりした場合です。急激な負荷増はオーバーユースによる足底筋膜炎を招きます。特に坂道や階段はふくらはぎ・足底への負荷が高く注意が必要です。
ランニングフォームの問題: 大股で踵からドスンと着地するフォームは、かかと周辺と足底筋膜に大きな衝撃を与えます。逆につま先寄りに着地しすぎるフォームも、ふくらはぎと足底筋膜への張力が増してリスクとなります。
「疲労時やオーバーペース時にはフォームが乱れやすいので、無理のない自然なフォームを心がけましょう。」また、股関節やハムストリングスの硬さ、体幹や臀部の筋力不足はフォーム悪化につながります。例えば股関節の可動域が狭いと着地衝撃をうまく逃がせず足裏に集中したり、体幹が不安定だと着地ごとに余計な負担が足にかかります。
シューズ選びと摩耗: ランニングシューズのクッション性や安定性が落ちると足底筋膜への衝撃が増えます。シューズの寿命(一般に走行距離500〜800km程度)を過ぎて底がすり減っていたり、ミッドソールがヘタっていないでしょうか?撃吸収性能が低下しており、靴底のクッションが死んだ状態では足底筋膜がダメージを受けやすくなります。
さらに、自分の足に合ったシューズかどうかも重要です。
「オーバープロネーション傾向がある場合は、安定性シューズやモーションコントロールシューズが適しています。」逆にアーチが高くプロネーションが少ないなら、クッション性に優れたシューズを選ぶと衝撃吸収を補えます。靴選びを誤ると、走行中に足が安定せず筋膜に余計な負荷がかかります。
日常の履物と習慣: 日中にハイヒールや革靴で足を圧迫し、帰宅後すぐランニングするなど、足環境の急変もストレスになります。また自宅で長時間裸足やスリッパで過ごすことも、土踏まずへのサポートがなく足底筋膜を伸ばしっぱなしにするため良くありませんは、室内でもアーチを支えるスリッパやサンダルを使用する方が回復を助けます。
以上を踏まえ、ご自身の状況を振り返ってみてください。「ふくらく足が内側に倒れる」「最近靴底がすり減ったシューズで走っていた」など心当たりがあれば、それが根本原因かもしれません。原因がわかれば対策の糸口も掴めます。
次は具体的な治療法とセルフケアに移りましょう。足底筋膜炎の治療は多くの場合、手術などの侵襲的手段に頼らず保存療法(セルフケアと非手術的治療)で改善可能です。
ガイドラインで推奨される実践的なケア方法を紹介します。今日から取り入れられるものばかりですので、ぜひ試してください。
アイスマッサージ(冷却療法)の活用:痛みや炎症が強いとき、手軽で効果的なのがアイスマッサージです。足底筋膜炎におけるアイスマッサージとは、冷却とマッサージを同時に行うセルフケア方法で、やり方は簡単です。
500mlのペットボトルに水を入れて凍らせ、それを床に置き、土踏まずをそのボトル上に乗せ、かかとからつま先までゴロゴロと転がしましょう。ポイントは力を入れすぎず心地よい圧で、足裏全体をマッサージすること。5〜10分る炎症抑制とマッサージによる血流改善が同時に期待できます。
これを1日2〜3回、特にランニング後や痛みが強い日の夜に実践すると効果的です。
アイスマッサージは患部の痛みを和らげる応急処置として有用ですが、長期的な治癒のためには他のケアも組み合わせる必要があります。次のストレッチと併用し、総合的にアプローチしましょう。
ストレッチ・筋膜リリースで柔軟性を取り戻す
足底筋膜炎の改善には、足裏からふくらはぎにかけての柔軟性向上が欠かせません。筋肉の硬さが原因の一つである以上、ストレッチと筋膜リリースで筋・筋膜をほぐすことが治療の柱となります。
プラントアー筋膜ストレッチ(足底筋膜ストレッチ)
最も代表的なのはタオルストレッチです。長座体前屈の姿勢で、タオルやバンドを足裏に引っ掛け、つま先を自分の方に引き寄せます。足裏からアキレス腱までが伸びるのを感じながら15〜30秒キープし、左右各2〜4回ずつ行います。朝起きてすぐ、あるいは長時間座った後など「足が冷えて硬くなった状態」で行うと、歩き始めの痛み軽減に役立ちます。就寝前にも実施すると、寝ている間に筋膜が縮こまりにくくなり翌朝が楽になります。
ふくらはぎ(腓腹筋・ヒラメ筋)ストレッチ
壁や段差を使ったストレッチを毎日行いましょう。壁に手をつき、一歩後ろに引いた足のかかとを床につけたまま前膝を曲げてアキレス腱〜ふくらはぎを伸ばす方法が一般的です。これも15〜30秒キープを2〜4回、1日に3〜5セット行うと効果的です。段差を使う場合は、つま先だけ段に乗せてかかとを沈める「階段ストレッチ」が有効です。どちらもヒラメ筋と腓腹筋の両方を伸ばす目的で、膝を伸ばした状態(腓腹筋狙い)と軽く曲げた状態(ヒラメ筋狙い)でそれぞれ伸ばすと良いでしょう。
足趾のストレッチ
足趾(足の指)を伸展させるストレッチも足底筋膜に効果的です。椅子に座り、痛い側の足を反対の太ももに乗せ、手で足趾をつかんでゆっくり後方に反らせます。このとき足の指から足裏アーチにかけて心地よい伸びを感じるようにしましょう。テレビを見ながらでもできる簡単ストレッチです。
筋膜リリース
硬くなった筋膜や筋肉を柔らかくするには、フォームローラーやマッサージボールを用いた筋膜リリースも有効です。足裏ならゴルフボールや硬式テニスボールを踏んで転がす、ふくらはぎやハムストリングスはフォームローラーに体重を乗せてコロコロ転がすなど、自分で筋膜を緩めるケアを取り入れてください。痛気持ちいい程度の圧でじんわりほぐすのがコツです。特に朝起きる前に足裏を軽くマッサージすることで、起床時の激痛を軽減できます。
ストレッチや筋膜リリースは即効性と予防効果があります。朝昼晩の1日複数回に分けて行うことで、足底筋膜の柔軟性が高まり痛みが和らぐだけでなく、再発防止にもつながります。大切なのは継続です。痛みが軽減してもすぐやめず、柔軟性維持の習慣として続けましょう。
インソールの活用
日中のセルフケアに加えて、夜間やランニング時のサポート具も検討しましょう。
スプリント(夜間装具)
これは足首を直角程度に保つよう固定する装具で、寝ている間に足底筋膜とアキレス腱を軽くストレッチした状態にします。足底筋膜炎の人は睡眠中に足首が伸びきって筋膜が短縮したまま固まり、起床時の痛みを引き起こします。スプリントを装着すれば寝ている間も筋膜が伸展され、朝の激痛を軽減できます。慣れるまで違和感がありますが、1〜3ヶ月の装着で効果が現れることが多く、医療ガイドラインでも推奨されています。最近はソフトタイプのブーツやソックス型のスプリントも市販され、快適性も向上しています。
インソール(中敷)や矯正用足底板
ランニング時や日中の歩行を助けるなら、靴に入れるアーチサポート付きインソールが有効です。土踏まずを持ち上げて足底筋膜の負担を減らし、足の過剰な回内を抑える効果があります。市販のインソール(既製品)でも効果は期待できますが、症状が強ければ整形外科やスポーツクリニックでカスタムメイドの矯正インソールを作ってもらうのも一案です。研究によれば、インソール単独では完治に至らなくとも痛みの軽減には寄与することが多いようです。特に扁平足や過回内が顕著な方、あるいは立ち仕事が多く日中も足底に負荷がかかる方は、常用する靴にインソールを入れてサポートすると良いでしょう。
足底筋膜炎用ソックスやテーピング
最近では足底筋膜炎対応のコンプレッションソックスも登場しています。足首から土踏まずに適度な圧をかけ血流を促進し、日中のアーチを支えるため歩くときに着用すると痛み軽減が期待できます。また、運動時にはキネシオロジーテープやアスレチックテープで足裏をテーピングする方法もあります。テープでアーチを補強し足底筋膜をサポートすることで、短期的な痛み緩和に役立ちます。キネシオテープなら比較的動きを妨げずサポートできるため、走るときはこちらが好まれます。ただし正しい貼り方を習得する必要があるので、専門家に教わるかガイドを参照して実践しましょう。
靴の選び方(アーチサポートとクッション性)
足底筋膜炎と向き合う期間は、履く靴にも細心の注意を払いましょう。間違った靴選びは治りを遅らせますが、適切な靴は回復を助けてくれます。
ランニングシューズ
すでに触れたように、オーバープロネーション気味ならモーションコントロール系やスタビリティ系のシューズで内側アーチサポートがしっかりしたものを選びましょう。クッション性が十分にあり、かかとの安定性が高いモデルがおすすめです。逆にハイアーチの場合は、ニュートラル系でクッション重視のモデルを選び、着地の衝撃を和らげることを優先します。共通して重要なのは「劣化した靴を使わない」ことです。靴底をチェックし、摩耗が激しい場合は買い替えを検討しましょう。目安として500〜700km走ったら次のシューズを準備するのが理想です。
普段履きの靴
通勤や普段の生活でも、アーチをサポートしクッション性のある靴を履くよう心掛けましょう。硬い革靴や底の薄い靴は避け、衝撃吸収に優れたウォーキングシューズやスニーカーが理想的です。職場でドレスコードがある場合も、市販のインソールを使用するだけで違います。女性の場合は、ヒールの高い靴は症状悪化につながるため避け、ローヒールやウェッジソールなど安定性が高い靴を選ぶようにしましょう。また、自宅では裸足で歩かず、少しクッションのあるスリッパや室内履きを使用して足裏を保護してください。
走れるタイミングまでの代替シューズ
痛みが強く走れない期間でも完全な休足は難しいものです。そこで、例えば厚底でクッション性が非常に高いシューズ(いわゆる“マックスクッション”タイプ)をウォーキングに使い、足底への負担を軽減することが有効です。「走らないからどんな靴でも良い」と考えるのではなく、回復期こそクッション性が高い靴で足を保護する意識を持つことが重要です。
これらを組み合わせて実践することで、多くの足底筋膜炎は数ヶ月以内に改善します。ただし、人によっては痛みが頑固に残る場合もあります。その際は医療機関で体外衝撃波療法(ESWT)やステロイド注射、超音波ガイド下刺鍼(Tenotomy)などの先進治療を検討することもあります。しかしこれらはあくまで最終手段です。まずはセルフケアを積み重ねて、足底筋膜炎を克服する方法を模索しましょう。
第3章:走ってもいいのか?判断とトレーニング戦略
足底筋膜炎に悩むランナーにとって最も気がかりなのは、「痛みがあっても走って良いのか、それとも休むべきか?」という問題ではないでしょうか。ここでは専門家の意見をもとに、痛みの程度による判断基準と、走れない期間のトレーニング戦略について考えてみます。
足底筋膜炎に対する最善の治療は安静(休息)です。しかし市民ランナーにとって、長期間まったく走らないのは精神的にも辛いもの。幸い、軽度の痛みであれば、適切な管理のもと走りながら治すことも可能です。
理学療法士のショーン・ジョイス氏は、「軽度の足底筋膜炎であればランニングを継続してもよいが、適切なリハビリ計画を並行して実施すべきだ」と述べています。
痛みの程度による判断基準
- 走るうちに痛みが和らぐ場合: これは筋肉の硬さに起因する痛みである可能性が高く、ウォームアップ後に症状が軽減するなら慎重に走ってもよいとされています。ただし、ランニング後には必ずアイシングやストレッチを行い、ふくらはぎや足底の柔軟性向上に努めることが前提です。
- 走っている間ずっと痛みが続く、または悪化する場合: これは注意が必要なサインです。ジョイス氏は、スタートからフィニッシュまで痛みが持続する場合は、ただちにランニングを中止すべきと警告しています。痛みを押して続ければ組織損傷が進み、不自然な動作パターンで他の部位まで痛めたり、重症化して長引く恐れがあります。
- 歩行時にも激しい痛みがある、少し走っただけで悪化する場合: このような重度のケースでは、整形外科医のレイチェル・トリシェ医師も「高強度のランニングは避けるべき」と述べています。痛みで正常なフォームが維持できない状態で無理に続けると、回復を遅らせる原因になります。
以上をまとめると、痛みが軽くウォームアップで緩和する場合のみランニングを継続し、それ以外の場合は休養または別メニューへの切り替えが賢明です。特に「痛みが出ても我慢できる範囲なら走っていい」という考えは危険であり、専門家は痛みを過小評価しないよう強調しています。多少の違和感はランナーにつきものですが、足底筋膜炎の痛みは身体からの重要なサインです。無視せず身体の声を聞くことが長期的な回復につながります。
走って良いレベルの痛みでもトレーニング内容は調整が必要
走っても良いレベルの痛みだったとしても、発症前と同じメニューをこなすのは避けるべきです。足底筋膜炎の症状がある間は、トレーニング内容を見直し調整する必要があります。以下に見直しのポイントを挙げます。
距離と頻度の調整
まずは全体の走行距離と回数を減らします。例えば週5回走っていた人なら週3回に、1回10km走っていた人は5kmに短縮するなど、痛みが悪化しない範囲に設定します。よく言われるルールは「前週までの距離や頻度の10%以上は増やさない」ことです。痛みが治まってきても段階的に増やし、急激な負荷増加は避けましょう。
ペースと路面の配慮
スピード練習やインターバル走、閾値走といったハードなメニューは中止しましょう。ペースは会話ができるジョグ程度に抑え、心肺よりも足への負荷軽減を優先します。また、舗装路(アスファルトやコンクリート)は硬く衝撃が強いため、可能であれば芝生や土のトレイルなど柔らかい地面を選んで走ると足底への負担が減ります。トラック(タータントラック)でのジョグも効果的です。
下り坂や段差の回避
坂道の下りは足底へのブレーキ負荷が大きく、階段の下りも同様です。足底筋膜炎の間はできる限り下り坂トレーニングは避け、フラットな道を選びましょう。どうしても坂のある道を走る場合、上りはゆっくり小刻みなストライドで、下りは歩いて降りるくらい慎重に対応しましょう。
ウォーミングアップとクールダウン
いつも以上に入念にウォームアップを行います。少なくとも5〜10分は歩行やゆるいジョグ、ダイナミックストレッチで体を温め、足首やふくらはぎ周りを動かしてから走り始めましょう。クールダウンも怠らず、ランニング後はストレッチとアイシングで足裏〜ふくらはぎをケアします。
痛み日誌をつける
走った日・距離・痛みの具合を記録しておくと、負荷と痛みの関係性が見えてきます。「○km以上走ると翌朝の痛みが強い」などのパターンがわかれば、上限距離を設定しやすくなります。記録は客観的な判断材料となり、復帰プランにも役立ちます。
クロストレーニングの選択肢
痛みが強くどうしてもランニングを休まざるを得ない場合でも、心配はいりません。クロストレーニングで心肺機能を維持しつつ、足底への負荷を避ける方法があります。おすすめのクロストレーニングをいくつか挙げます。
- 水中ランニング(アクアジョギング): プールで専用の浮力ベルトを着けて行う水中ウォーキング・ランニングです。浮力で体重が軽減され、足底にほぼ負荷をかけずにランニング動作が可能です。心肺機能も維持できます。
- エリプティカル(クロストレーナー): ジムにある楕円形運動マシンも足への衝撃が少なく、関節に優しい有酸素運動です。長時間の有酸素運動にも適しています。
- サイクリング: 自転車でのサイクリングも足底への衝撃がほぼありません。特に柔らかめの靴で回転数高め(ケイデンス多め)に漕ぐと、心肺機能を効率よく鍛えられます。
- 水泳: 全身運動ながら足に衝撃がないため、フリー(クロール)やバック(背泳ぎ)での水泳は足首の柔軟性向上にも効果的です。足底筋膜炎の方は、足首への負担が少ない泳法を選びましょう。
- 筋トレ・体幹トレーニング: 臀筋群や体幹、股関節周りを鍛えることでフォーム改善に役立ちます。足底への衝撃を避けながら筋力強化が可能で、復帰後のパフォーマンス向上にもつながります。
クロストレーニングを組み合わせて心肺機能を維持しつつ、足底筋膜を休ませることが理想的です。「走らないと不安」という心理は多くのランナーが抱えますが、ケガの回復を最優先に考えることで結果的に早く元の走力に戻ることができます。「今休むのは将来の走りのため」と割り切り、可能な運動を継続しながら復帰を待ちましょう。
続きはまた明日です!お疲れさまでした!
公式LINEにご登録お願いします。
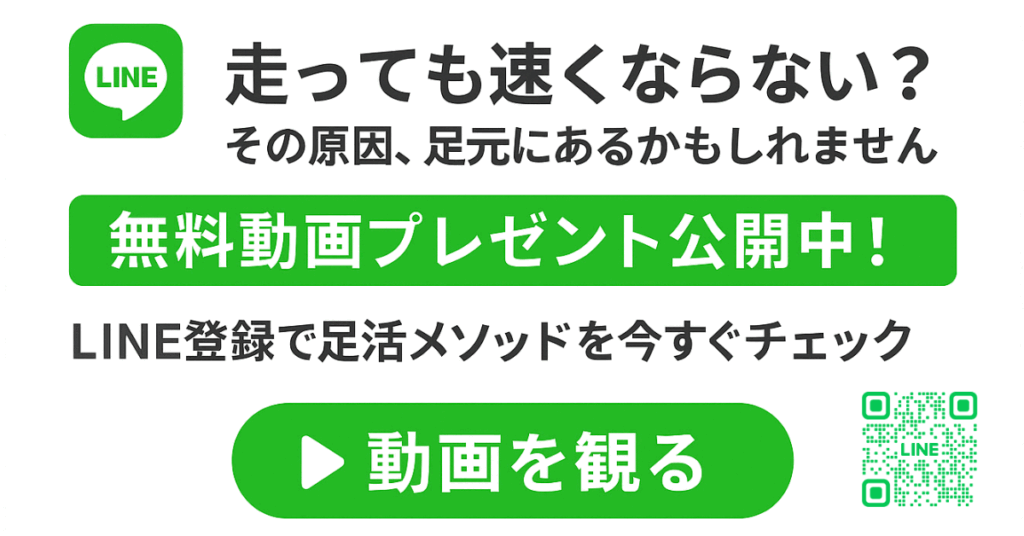
お知らせ:足活体操教室(足から全身を整えて楽しく運動できる体をつくる)
内容: ブログ内参考
足からの整体ケア&全身体操
場所:北九州小倉北区中井4-5-24-1F:のうだ整骨院内(Tel:093-563-3325)
時間:午前11時~12時
料金:入会金:5,000円 月会費:4,000円
個別指導:1時間:10,000円(予約制:オンライン可)