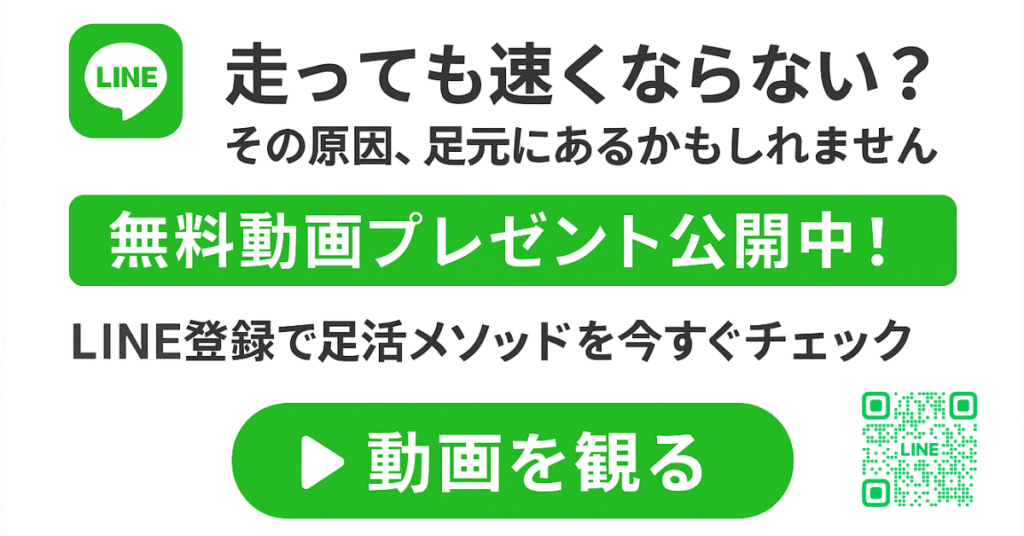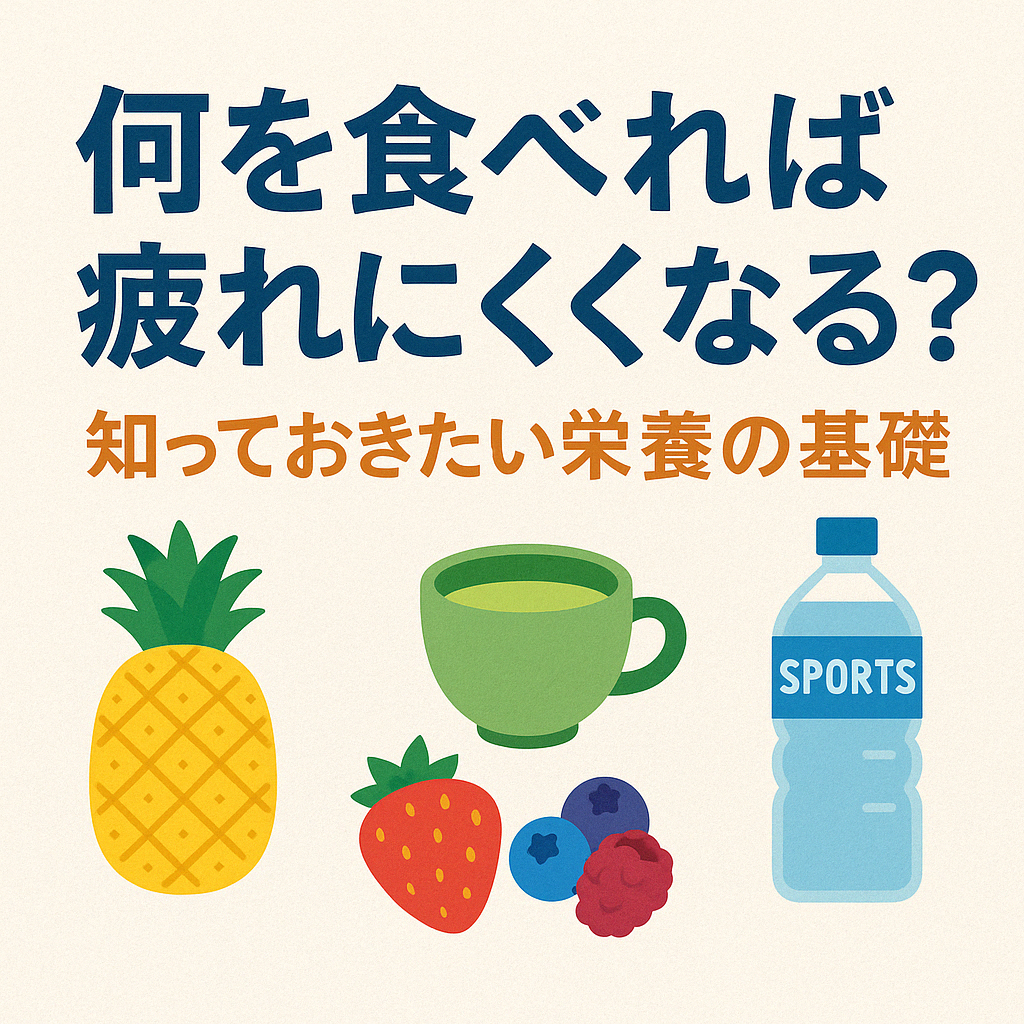第1章:なぜ「栄養」が疲労に関係するのか?

「疲れた……でも走りたい」「最近、トレーニングの質が落ちてきた気がする」
そんな風に感じていませんか?特に市民ランナーは、フルタイムの仕事、育児、家事、そして限られた時間でのトレーニング。プロのように休息を確保したり、専属の栄養士を付けたりすることはできません。
そんな私たちにとって、「疲れにくい体」をつくる最も現実的なアプローチは――ずばり、“日々の食事”です。
疲労には大きく分けて2種類あります。
ひとつは、筋肉や関節の使いすぎによる身体的な疲労。もうひとつは、ストレスや睡眠不足、思考の過負荷による精神的な疲労(脳の疲労)です。
そしてこの両方に密接に関係しているのが「栄養」です。
筋肉疲労を回復させる“素材”が不足していないか?
筋肉は、トレーニングによって一度「壊す」ことではじめて強くなります。
しかし壊れた筋肉を修復し、再び強くするには、“材料”が必要です。その材料とは、たんぱく質、ビタミンB群、ミネラルなどです。
特にランナーは汗を大量にかくため、亜鉛やマグネシウムといった微量栄養素が失われがち。これらが不足すると、筋肉痛が長引いたり、関節のトラブルが増えたりします。
食事の内容に偏りがあると、頑張ってトレーニングしても、その成果を十分に引き出せないことさえあります。
実は“脳の疲労”が走りに影響している
もう一つ見逃せないのが、脳のエネルギー不足=意志力の低下です。
たとえば、長距離ランの後半で「もう無理…」「歩こうかな」と感じたことはありませんか?
その感覚、実は筋肉が限界に達したわけではなく、脳が“もう頑張れない”と判断している状態かもしれません。
脳のエネルギー源は、ほぼ100%がブドウ糖(血糖)です。血糖値が下がると、脳は「今は無理しないほうがいい」と判断し、パフォーマンスを抑えてしまいます。
つまり、血糖値の安定=意志力の維持なのです。
このことからも、朝食を抜いたり、炭水化物を過剰に控える食事法は、マラソンに向かないことがわかります。
現代人の“食事疲れ”に注意
もう一つ、疲労に直結する現代的な要因として、「糖質過多+栄養素不足」という食生活の矛盾があります。
コンビニ弁当や菓子パン、加工食品に頼りがちな生活は、カロリーは高いのに必要なビタミンやミネラルが圧倒的に不足しています。
糖質が多すぎると、血糖値が急激に上下して、イライラしやすい・集中できない・疲れが取れないといった状態に陥ります。
さらに、これらの食品には炎症を引き起こす成分(加工油脂、添加物など)も多く含まれており、筋肉や関節の回復を妨げる要因にもなります。
「食べること=疲労回復の第一歩」
トレーニングだけでは、疲れにくい体は手に入りません。
食事を変えること、それが“回復力”を高め、日々の疲れにくさにつながります。
無理な制限や特別な栄養法は不要です。
まずは、「筋肉の材料」となるたんぱく質、「脳のガソリン」となる炭水化物、そして「炎症を抑える」野菜や果物など、バランスの良い食事を意識することから始めましょう。
第2章:マラソンと血糖値の深い関係
マラソン大会やロング走の後半、「突然ペースが落ちる」「気持ちが切れて歩きたくなる」そんな経験はありませんか?
脚力や心肺機能だけの問題と片付けがちですが、実はその原因のひとつに血糖値の低下が関係している可能性があります。
血糖値が落ちると、脳のエネルギーが不足し、“もう無理”という信号を出してしまう――。
この章では、マラソンと血糖の知られざる関係性に迫ります。
脳の燃料は「グリコーゲン」
まず、知っておきたいのは「脳は100%ブドウ糖(=グリコーゲン)で動いている」という事実です。
筋肉のグリコーゲン(糖質の貯蔵形態)は、レースの前日までの食事によって補充され、走っている最中に使われていきます。
ところが、当日の朝に食べた糖質は、筋肉のグリコーゲンには変わらないことをご存じでしょうか?
筋グリコーゲンへの補充には、少なくとも一晩、長ければ24時間以上が必要とされます。
つまり、当日の朝食が「エネルギー源」になるのではなく、「脳のコンディションを整えるスイッチ」になるのです。
朝食で「脳のやる気スイッチ」が入る
レースや長距離走では、交感神経が優位になる「闘争か逃走反応(Fight or Flight)」が自然に起こります。
これはストレスホルモン(アドレナリンやノルアドレナリン、コルチゾールなど)の分泌により、心拍が上がり、血糖値が一時的に上昇して、全身が“戦闘モード”に入る生理反応です。
このとき、脳が血糖値の低下を感じていると、出し惜しみを始めるのです。
人間の体は「飢餓」を生き延びるようにできているため、「この先いつ食料にありつけるかわからない」という判断のもと、ペース配分を勝手に下げてしまうという説(ティム・ノックス博士)もあります。
言い換えると、朝食で血糖値をゆるやかに上げることができれば、脳が“まだ頑張れる”と判断してくれるのです。
これが意志力、集中力、走りの粘りにつながります。
血糖値と意志力の意外なつながり
心理学の実験でも、血糖値と自己コントロール力(意志力)の関係は立証されています。
たとえば、ある実験では、被験者に甘味料入りの飲み物と、砂糖入りの飲み物を与えたグループで、明らかに意志力の持続力に差が出たことが報告されています(ケリー・マクゴニガル著『スタンフォードの自分を変える教室』)。
また、血糖値が低い人ほど、衝動的になりやすく、キレやすくなる傾向があるという研究も。
つまり、脳にエネルギーが供給されていない状態では、集中力も判断力もガタ落ちになるということです。
血糖値を「急上昇」させず、「安定」させよう
ただし、注意したいのは、糖質の“質”と“タイミング”です。
朝から菓子パンや清涼飲料水など、GI値の高い糖質(血糖値が急上昇しやすいもの)を摂ってしまうと、その後の血糖値の乱高下でかえって疲れやすくなります。
おすすめは、
- 白米やお餅+納豆や卵などのたんぱく質を組み合わせる
- 玄米おにぎり+味噌汁などの和朝食
- バナナ+ヨーグルト+ナッツなどの軽食
といった「血糖値が安定しやすい朝食」です。
特に長時間トレーニングをする日や、レース当日の朝は、胃腸にやさしく、吸収がゆるやかな糖質を摂ることがカギになります。
小さな食習慣が、後半の“粘り”を生む
マラソンは、筋力や心肺機能の勝負だけではありません。
レース後半の“粘り”を決めるのは、脳がどれだけ最後まで「頑張れる」と判断しているか――つまり「血糖値のゆるやかな安定」によって左右されるのです。
朝食をおろそかにしないこと。
そして、日頃の食習慣でも血糖値が安定するよう意識すること。
これだけでも「疲れにくい体」「最後まで粘れる脳」はつくれます。
次章では、こうした血糖値の安定にも関わる、「炎症」と「疲労」の関係について深掘りしていきましょう。
第3章:疲れにくい体をつくる「抗炎症」の栄養戦略
「寝ても疲れが取れない」「筋肉痛が長引く」「走るたびに関節が痛む」
こんな悩みを抱えている市民ランナーは少なくありません。
このような慢性的な疲労感や体の不調の背景にあるもの――
それが「炎症」です。
炎症というと、ケガや熱、腫れなどをイメージしがちですが、実はもっと静かに進行する“見えない炎症(サイレント・インフラメーション)”が、日常的な疲れや不調の根本原因となっていることが多いのです。
炎症とは「治すための反応」だが…
炎症とは、本来は体を守るための自然な反応です。
風邪をひいたときに熱が出る、ケガをしたときに腫れる。これらはすべて「治そう」とするための生体反応です。
ところが、トレーニングによって筋繊維が微細に傷ついたり、関節に繰り返しの負担がかかることで、「炎症モード」が長引きすぎることがあります。
また、加工食品や高脂肪・高糖質の食事も、体の中で慢性的な炎症を生み出す要因になります。
炎症が長引けば長引くほど、体の回復は遅れ、免疫や代謝、ホルモンバランスにも悪影響が出てきます。
つまり、“疲れやすい体”は、炎症に支配されている体でもあるのです。
食べ物で“火を消す”ことができる
ではどうすればよいのか?
そこで注目すべきが、「抗炎症作用のある栄養素」です。
薬に頼らず、日常の食べ物や飲み物で、炎症をやわらげることができるのです。
特に抗炎症に効果的な食材として、次のようなものが挙げられます。
- 緑茶:ポリフェノール(カテキン)の強力な抗酸化作用で、軟骨の炎症を抑える
- ベリー類:アントシアニンによってTNF-αやNF-κBといった炎症性物質を抑制
- パイナップル:酵素ブロメラインが、筋肉や関節の腫れをやさしく鎮める
- ショウガ・ターメリック(ウコン):抗炎症スパイスの代表格
- オメガ3脂肪酸(青魚・亜麻仁油など):炎症性物質の発生そのものを減らす
これらは、どれも副作用のない“天然の抗炎症薬”です。
日々の食事に意識的に取り入れることで、リカバリー力が格段にアップし、疲れにくくなっていきます。
サプリより「組み合わせの力」
「じゃあサプリで摂ればいいのでは?」と思うかもしれませんが、実は食材の“組み合わせ”によって吸収率が上がるという特性も見逃せません。
たとえば、
- パイナップルの果肉と芯を両方食べることで、ブロメラインの効果が最大化
- ベリーとヨーグルトを一緒に摂ると、乳酸菌の整腸作用と相乗効果
- 緑茶と魚(和食)を一緒に摂ることで、抗酸化と脂肪代謝が促進
自然の食品は“単体で完結する”のではなく、複数の栄養素が連携して作用する仕組みになっているのです。
疲労の裏には「微細な炎症」がある
ここで改めて、次のような状態に心当たりがある方は、「抗炎症」の視点から食事を見直すべきです。
- 関節や筋肉が慢性的に重い・だるい
- 風邪や微熱が治りにくい
- 食後にやたら眠くなる、だるくなる
- 甘いものや揚げ物がやたら欲しくなる
- いつもイライラ・気分が落ち込むことが多い
これらはすべて、「体の中に炎症が起きているサイン」である可能性があります。
「リカバリー=栄養で整える」意識を持とう
トレーニングに励むだけでなく、その後にどう回復するかが、走力の差を生む時代です。
ケガや不調に悩まされてから対処するのではなく、「疲れをためない体づくり」のために日常的な“抗炎症習慣”を取り入れていきましょう。
高価な食材やサプリに頼る必要はありません。
「疲れた日ほど、体にやさしいものを食べよう」
「今日はベリーとお茶を意識的に摂ってみよう」
そんな小さな積み重ねが、明日の走りを変えてくれるはずです。
次章では、こうした抗炎症食材の代表格でもある「パイナップル」と「緑茶」にフォーカスして、より具体的な効果と活用法を紹介していきます。
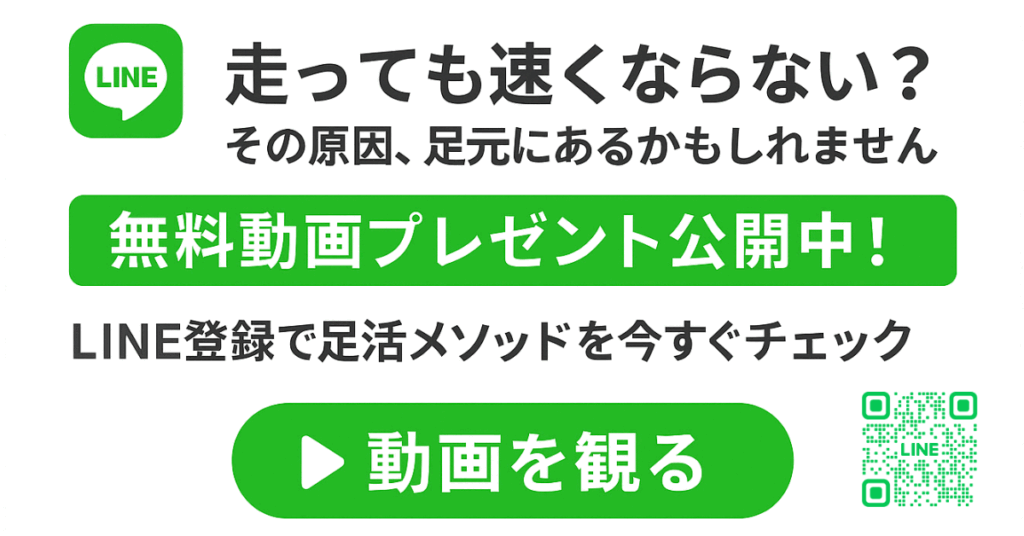
第4章:毎日の食事に「パイナップル」と「緑茶」を
「サプリに頼らずに、食べ物で疲れにくい体をつくりたい」
そう考えるランナーにとって、ぜひ日常的に取り入れてほしいのがパイナップルと緑茶です。
意外かもしれませんが、この2つはどちらも強力な抗炎症作用を持つ“天然の回復サポーター”。
味もなじみ深く、無理なく続けられるのが大きな魅力です。
パイナップルに含まれる“回復酵素”ブロメライン
パイナップルに含まれる酵素ブロメラインは、たんぱく質を分解して消化を助ける働きで有名ですが、実はそれだけではありません。
ブロメラインは、
- 関節炎や筋肉痛などの炎症を抑える
- 免疫の働きを整える
- 腫れや浮腫を軽減する
といった、まさに「走った後のリカバリー」に最適な働きをしてくれるのです。
特にトレーニング後の筋肉の違和感や、関節まわりの痛みに悩まされている方にはおすすめです。
「肉を食べたあとに胃が重くなる」「疲れていて消化が悪い」そんな時にも、消化酵素として力を発揮してくれます。
芯ごと食べるのが◎!効果を最大限に引き出すコツ
ブロメラインは、実は果肉と芯に別々の種類が含まれており、両方合わせてこそ効果が高いと言われています。
甘くて食べやすい果肉だけでなく、芯の部分をスムージーにしたり、煮込みに使ったりするのがポイントです。
また、ブロメラインは加熱にやや弱いため、なるべく生で摂るか、低温調理が◎。
市販の冷凍カットパインを活用するのも、忙しい市民ランナーには現実的な選択です。
どうしても毎日摂るのが難しい方には、サプリメントでの摂取も可能です。
ただし、「食べ物で摂ること」を基本にすると、他の栄養素(ビタミンC、食物繊維)も一緒に補えるため、より効率的です。
緑茶は“飲む抗酸化サプリ”だった
一方、緑茶は日本が誇る抗酸化食品です。
中でも注目したいのが、緑茶に豊富に含まれるポリフェノールカテキン。
特に「エピガロカテキンガラート(EGCG)」は、
- 炎症を抑制する
- 関節の軟骨細胞を守る
- 体内の酸化ストレスを軽減する
- 悪玉コレステロールの抑制
などの働きを持つことがわかっています。
また、緑茶には抗酸化作用だけでなく、
- 血糖値の安定
- 集中力の持続
- 脂肪燃焼の促進
といったランナーに嬉しい複数のメリットがあります。
カフェインとの付き合い方を知っておこう
ただし緑茶にも、少量ながらカフェインが含まれています。
このカフェインは「闘争か逃走反応」を引き起こすスイッチでもあり、トレーニング前にはやる気を高める効果があります。
一方で、就寝前に摂ると睡眠の質が低下し、疲れが取れなくなるリスクもあります。
そのため、
- 午前中やトレーニング前に飲む
- 夜はカフェインレス緑茶や焙じ茶、麦茶に切り替える
といった工夫をすることで、緑茶の効果をしっかり活かしながら、リズムも崩さない生活ができます。
パイナップル×緑茶=最強コンビ
実はこの2つ、一緒に摂ると理想的な組み合わせです。
パイナップルが「抗炎症+消化サポート」、緑茶が「抗酸化+代謝改善」というそれぞれの役割を果たし、体のリカバリーと疲労軽減に相乗効果を発揮します。
例えばこんな取り入れ方もおすすめです:
- 朝食にカットパイン+緑茶
- 昼食後にパインヨーグルトと緑茶
- トレーニング後の軽食にスムージー+緑茶ティー
どれも特別な準備はいらず、すぐに実践できる方法ばかりです。
続けやすさが“最大の栄養”
栄養法において最も大切なのは、「特別なことを1日やる」よりも「シンプルなことを毎日続ける」ことです。
パイナップルも緑茶も、スーパーやコンビニで手に入る身近な食品です。
「今日は走ったから、食後にパインと緑茶をセットで」
そんな風に、習慣化していくことで、体の中から疲れにくさをつくっていくことができるでしょう。
第5章:自然の力を味方につける「ベリー」の底力
「最近、回復が遅い」「年齢とともに疲れやすくなった気がする」
そんな悩みを抱える市民ランナーにとって、自然の抗酸化食材=ベリー類は、心強い味方になります。
見た目が鮮やかで甘酸っぱいベリーたち――
実はその小さな実の中に、炎症を抑え、酸化ストレスから体を守り、細胞を若々しく保つパワーが詰まっているのです。
「ベリー=ブルーベリー」だけじゃない!
「ベリー」と聞いて真っ先に思い浮かぶのはブルーベリーかもしれませんが、それだけではありません。
健康効果の高いベリーには、実に多くの種類があります。
- ラズベリー(きいちご)
- ブラックベリー(黒いちご)
- ストロベリー(いちご)
- アサイー
- クコの実(ゴジベリー)
- スグリ(カシス)
- ザクロやチェリーもベリー的機能が強い果実
これらのベリーに共通するのは、アントシアニンをはじめとするポリフェノールが非常に豊富であるという点です。
アントシアニンは、目の健康をサポートする成分としても知られていますが、それ以上に、全身の「炎症・酸化・老化」から細胞を守る力があります。
「走る体」は“酸化”と“炎症”との戦い
ランナーの体は常に酸素を多く消費しています。
これはすなわち、活性酸素が体内に大量発生している状態でもあります。
活性酸素は、細胞を傷つけ、筋肉や関節の炎症を悪化させたり、老化を早める原因になります。
そのため、ランナーは意識的に抗酸化物質を摂る必要があるのです。
ベリー類は、ORAC値(抗酸化力の目安)で他の食品を圧倒しています。
| ベリー類のORAC値(100gあたり)
|————————-
| クコの実(ゴジベリー):10,000〜30,000
| アサイー:5,500以上
| ザクロ:5,000以上
| ブルーベリー:2,400
| ラズベリー:1,200
| イチゴ:1,550
たとえば、オレンジやブロッコリーと比べても、数倍〜数十倍の抗酸化力を持っているのがベリー類なのです。
「関節炎」や「疲労の蓄積」を防ぐ仕組み
ベリー類のすごさは、抗酸化作用にとどまりません。
実は、炎症を促進する物質(NF-κB、TNF-α、インターロイキン類)を抑える働きも持っています。
こうした慢性炎症は、関節痛・筋肉の硬直・倦怠感などを引き起こす原因。
また、脳の神経細胞の炎症を抑えることで、認知機能や集中力の維持にも貢献することが研究で示されています。
さらに、クコの実に含まれる「ベータクリプトキサンチン」や「ツェアキサンチン」は、関節の変性を防ぎ、柔軟性を保つ作用も確認されています(EPIC研究より)。
「ジュース・冷凍・ドライ」どう摂るのがベスト?
ベリー類は生で食べるのが理想ですが、コストや保存の観点からは冷凍・ドライ・ジュースという形で摂るのも現実的です。
- 冷凍ミックスベリー:スムージーやヨーグルトにそのまま
- ドライベリー(無添加):ナッツと一緒に間食に
- 100%ベリージュース:朝食時やトレーニング後に
- クコの実(ドライ):スープやおかゆ、ヨーグルトのトッピングに
1日あたりの目安量は30g〜50g程度。
毎日少しずつ摂ることで、体の中に“抗酸化の貯金”ができていきます。
疲れに強い体は「細胞から作られる」
ランナーの体は日々、ダメージと回復を繰り返しています。
ベリー類がもたらす細胞レベルでの修復と防御作用は、まさに「疲れにくさ」の土台となるものです。
- 疲れが抜けにくい
- 体調が不安定
- ケガが多くなってきた
- 年齢とともに回復が遅い
そんなときは、「足を休ませる」だけでなく「細胞を守る栄養を入れる」意識が必要です。
まずはヨーグルトにベリーをひとさじ
ベリー類は毎日の習慣に取り入れやすい食材です。
朝のヨーグルトにひとさじ混ぜるだけ、夜のおやつに冷凍ベリーを少しつまむだけでも、炎症の連鎖を断ち切る第一歩になります。
「走るための栄養」は特別なものではなく、自然の中に答えがある。
そう気づかせてくれるのが、ベリー類の力です。
次章では、栄養と同じく重要な「水分補給」について、市販のスポーツドリンクでは得られない“本当に必要な成分”と手作り方法を紹介していきます。
第6章:スポーツドリンクと水分補給の“新常識”
「水分はしっかり摂っているのに、なぜか疲れやすい」
「給水のタイミングがわからない」「ドリンクでお腹がゆれる感じがイヤ」
マラソンや長時間トレーニングをする市民ランナーにとって、水分補給は「命綱」です。
しかし、水分補給がうまくいっていないと、脱水やパフォーマンス低下だけでなく、消化不良や胃の不快感といった問題にもつながってしまいます。
この章では、市販のスポーツドリンクでは得られない「水分補給の真実」と、ランナーの体に本当に必要な水分の“質と量”についてお伝えします。
人間の体の60%は水でできている
まず基本として、人間の体は約60%が水分で構成されています。
筋肉細胞の約70%も水でできており、水分が不足することで、
- 酸素や栄養素の運搬が滞る
- 老廃物の排出が遅れる
- 神経伝達が鈍る
- 筋肉がこわばりやすくなる
といった影響が出てきます。
つまり、水分が不足した状態では「力が出ない」「疲れが取れない」「回復が遅れる」というのは当然のことなのです。
スポーツドリンク=万能ではない!
運動時の水分補給として真っ先に思い浮かぶのがスポーツドリンク。
しかし、市販されている多くの製品は果糖ブドウ糖液糖や人工甘味料を含み、実は運動中の胃腸に負担をかけやすいものも多く存在します。
特に注意したいのは、
- 果糖が多いドリンクは消化に時間がかかる
- 人工甘味料は腸内環境を乱す可能性がある
- 甘すぎるドリンクは血糖値の急上昇→急降下を招く
といった点です。
トレーニング中にお腹がゆれたり、胃が気持ち悪くなった経験がある方は、飲んでいる内容そのものを見直すべきかもしれません。
水分補給に必要な“3つの成分”
では、ランナーにとって理想的なスポーツドリンクには何が必要なのでしょうか?
実は、必要なのはたった3つだけ。
- 水分(当然ですが最も重要)
- 糖質(吸収を助け、脳と筋肉の燃料に)
- 電解質(特にナトリウムとカリウム)
この3つさえ揃っていれば、わざわざ高価なドリンクを買わなくても、自分で“最強の補給ドリンク”をつくることができます。
自作スポーツドリンクのすすめ
下記のような配合で、自宅で簡単にスポーツドリンクがつくれます。
【基本レシピ(500ml用)】
- 水:500ml
- 黒砂糖またはマルトデキストリン:大さじ1(約10〜15g)
- 塩:ひとつまみ(0.5g程度)
- レモン汁(お好みで):小さじ1〜2
※運動時間が60分未満であれば水のみでもOK。
※黒砂糖はミネラルも含まれた自然な糖質で、ゆるやかな吸収を促します。
※マルトデキストリンは吸収が早く、エネルギー効率が高いのでトレーニング時におすすめです。
ハチミツは天然甘味料ではありますが果糖が多く、消化に負担をかけるため運動中には不向きです。
水分補給のタイミングと量
いくら良質な水分を用意しても、飲むタイミングと量がずれていれば意味がありません。
【理想の水分補給の目安】
- 運動前:200〜300ml(30分前)
- 運動中:15〜20分ごとに100〜150mlずつ
- 運動後:失った水分+αの量を補う(体重1kg減=約1L必要)
のどが渇いたと感じた時点ですでに脱水が始まっていると考えましょう。
特に夏場や高湿度の環境では、意識的な補給が必要です。
また、冷たすぎるドリンクは胃を冷やしすぎて消化を妨げることもあるため、常温〜少し冷たいくらいがベストです。
水道水にレモンを加えるだけでも効果あり
「浄水器もないし、ドリンク作りも面倒…」という方には、レモン汁を水に数滴加えるだけでも、かなり違います。
レモンのクエン酸が、
- 水道水に含まれるカルキ(消毒成分)を中和
- pHを整えて吸収を促進
- 疲労物質の排出を助ける
といった働きをしてくれるからです。
もちろん、できる範囲で無理なく続けることが一番大切です。
「飲む内容とタイミング」で体の反応は大きく変わる
市民ランナーにとっての水分補給は、単なる水分摂取ではなく、“走る力”そのものです。
パフォーマンスを維持し、トレーニング効果を最大化するためには、何を・いつ・どれだけ飲むかに敏感になっていきましょう。
次章では、栄養・水分と同じくらい大切な「食事習慣」について、日々の疲労を軽減し、パフォーマンスを支える5つの食習慣のルールを紹介します。
第7章:忙しくても疲れをためないための食習慣5ヵ条
仕事・家事・育児――そしてランニング。
限られた時間とエネルギーのなかで日々を走り抜ける市民ランナーにとって、食事は単なる栄養補給ではなく、「回復の柱」です。
しかし、毎日完璧な食事を用意するのは現実的ではありません。
そこで重要になるのが、頑張らなくても疲れをためにくい「習慣のルール」を持つことです。
この章では、忙しいあなたの体と心を守る、5つの実践しやすい食習慣のコツをご紹介します。
【その1】「何を食べるか」より「どう組み合わせるか」
食事の基本はバランスです。
特別なスーパーフードを取り入れるよりも、毎日の食事に“栄養の三本柱”を整えることが重要です。
その三本柱とは…
- 炭水化物(ごはん・パン・麺など)
- たんぱく質(肉・魚・卵・豆腐など)
- ビタミン・ミネラル(野菜・海藻・果物など)
忙しいと単品メニューになりがちですが、単品ではなく“セット”で摂ることが、疲労軽減の第一歩です。
例)
× パン+コーヒー → ○ パン+卵+ヨーグルト
× おにぎりだけ → ○ おにぎり+味噌汁+納豆
【その2】「疲れたときこそ甘いもの」に注意!
疲れていると、つい甘いものに手が伸びがち。
しかし、菓子パンやスイーツ、清涼飲料水に含まれる高GI糖質は、血糖値を急上昇させたあとに急降下させ、一時的に元気になったようで、あとからどっと疲れが押し寄せるという落とし穴があります。
甘いものを完全にやめる必要はありませんが、
- 果物や干し芋など“自然な甘さ”に置き換える
- 甘いものを摂るなら、たんぱく質と一緒に
- 練習後30分以内なら糖質補給もOK(リカバリータイム)
という意識で摂れば、疲れをためずにうまくエネルギー補給できます。
【その3】「調理のハードル」を下げる工夫をする
料理は大事だとわかっていても、疲れている時に野菜を切ったり、食材を一から準備するのはしんどいもの。
そこでおすすめなのが、「あらかじめ下ごしらえしておく」「冷凍食材やカット野菜を常備する」など、調理のハードルを下げる工夫です。
- 休日にゆで卵をまとめて作っておく
- 冷凍ブロッコリー・カット野菜・味噌玉を常備
- サバ缶や豆腐など、すぐ食べられるたんぱく源を常備
「疲れたときでも“5分で栄養が摂れる環境”」を用意しておけば、食事を抜いたり菓子パンで済ませるリスクが減ります。
【その4】「食べる時間帯」で疲れ方が変わる
同じものを食べても、“いつ食べるか”によって体の反応は大きく違うということをご存知ですか?
特に意識したいのが、
- 朝食は、脳と意志力のエネルギー源(血糖値を安定させる)
- 夜遅くの食事は、消化負担・睡眠の質の低下につながる
- 運動後30分以内は“ゴールデンタイム”として栄養が吸収されやすい
忙しい日でも「食べる時間を意識するだけ」で、回復スピードが変わってきます。
【その5】「がんばりすぎない」をルールに
最後に、何より大事なのは、完璧主義にならないことです。
1日3食、完璧な食事を目指す必要はありません。
「1日1食、栄養バランスを意識できたらOK」くらいの気持ちで続けていくことが、本当の意味での“持続可能な食習慣”です。
食べられなかった日があっても、ジャンクな食事をしてしまった日があっても、そこで自分を責める必要はありません。
むしろ「昨日はたくさん走ったから、今日はしっかりリカバリーしよう」と思えるかどうかが、疲れないランナーの思考です。
食習慣を整えることは、未来の体への投資
私たち市民ランナーは、日常生活というフルマラソンの中で走っています。
だからこそ、「特別な食事」よりも、「日々を支える習慣」が力になります。
疲れにくい体は、一朝一夕にはつくれません。
しかし、今この瞬間の選択の積み重ねが、確実に未来の走りを変えていきます。
まずは今日の夕飯から、ほんの少しだけ意識してみませんか?
ベリーをひとつまみ、緑茶を一杯、納豆をひとパック――。
その積み重ねが、1ヶ月後、半年後のあなたの笑顔と自己ベストにつながっていきます。
お知らせ:足活体操教室(足から全身を整えて楽しく運動できる体をつくる)
内容: ブログ内参考
足からの整体ケア&全身体操
場所:北九州小倉北区中井4-5-24-1F:のうだ整骨院内(Tel:093-563-3325)
時間:午前11時~12時
料金:入会金:5,000円 月会費:4,000円
個別指導:1時間:10,000円(予約制:オンライン可)
「もう故障で立ち止まらない!“壊れずに走り続ける体”をつくる3つの原則」
LINE登録で無料プレゼント!